- トップ
- ブログ
ブログ
無事故で新年を迎えましょう!
2021年12月中に発生した交通事故は1年で最も多い月になりました。特に重傷者数、死亡者数は他の月に比べて約1.4倍高くなりました。
今月は、12月に重大事故がどのように起きているかを踏まえ、どのような走行を心がけたらよいかをみてみましょう。
薄暮時での歩行者の発見の遅れや、焦るあまりの安全運転義務違反により重大事故が起きている12月は仕事や帰省、年末年始の準備などでせわしく運転するドライバーが多く、わずかな運転ミスが重大事故につながります。
2021年12月中の重大事故がどのような場所で起きているか死亡事故件数の割合をみると、市街地が多く、なかでも交差点やその付近が多くを占め、見通しのよい直線道路では1月~11月の平均より増加しています。事故の状況別でみると、人対車両が約4割と最も多くなります。その大半が道路を横断中の歩行者と衝突しています。法令違反別では、わき見や安全不確認など安全運転義務違反が多くなります。昼夜別の死者数の割合を比べると、夜間の方が多く、死者の年齢層をみると、昼夜ともに65歳以上の割合が高くなっています。
12月は日の入りが早く、夜の時間帯が長くなります。ことに交通量が多い市街地では、薄暗くなった道路を渡ろうとしている歩行者の発見が遅れる可能性があります。なかでも65歳以上の歩行者は、暗い服を着ていることが多く、薄暗くなると目立たなくなります。また、身体機能の低下により危険回避の行動がとりづらくなっている可能性があるので、ドライバーが気づいたときには接触を避けられず重大事故に至るおそれがあります。
さらにドライバー側は、忙しいと運転中につい先のことや他のことを考えてしまいがちで、運転から注意がそれたり、焦るあまり安全確認を怠ったりして、重大事故を起こす危険性が高くなります。
12月の運転を安全に行うために
忙しい12月を安全運転で過ごし、安心してお正月を迎えるためにはどうしたらよいか、一緒に考えてみましょう。
・走行するときは…
早めにヘッドライトを点けましょう
地域によって異なりますが、冬の季節は午後3時を過ぎると薄暗くなり始めます。「まだ明るい」と感じていても徐々に視界は悪くなっており、事故が起きやすい状態に至ります。薄暗い道路で歩行者を発見したときに、危険回避することができるように、早めにヘッドライトを点けましょう。
携帯電話やカーナビの確認、エアコンの操作は車を安全な場所に止めて行いましょう
走行中に携帯電話やカーナビなどに目を移すと、その間に歩行者が道路に出てくるなど前方の交通状況が一変する可能性があります。特に12月は歩行者も車も多く、1秒にも満たないわき見が重大事故につながります。常に前を向いて運転できるように、携帯電話やカーナビの確認、エアコン等の操作は、車を安全な場所に止めてから
行いましょう。
車間距離をあけ、法定速度を維持し、周囲の安全確認を行いましょう
12月は何かと忙しくなることが多く、ドライバーは不十分な車間距離や速度超過など不安全な運転をしがちになります。同様に歩行者も横断歩道がない場所でいきなり横断してくるなど、危険な行動をとることがあります。視界を確保するため車間距離を十分にあけ、法定速度を維持し、周囲の安全確認を行いましょう。
定期的に車内を換気し、休息をとりながら運転しましょう。
暖房が効いた車内は徐々に酸素が不足するため、長時間換気しないと脳に酸素が行き届かず眠気をもよおします。また、忙しいと心身ともに疲れがたまり、脳が休もうとしてウトウトすることがあります。運転するときは、漫然運転を防ぐために、定期的に換気や休息を行い、安全運転に努めましょう。
事前の準備は…
冬用タイヤやバッテリーの点検など事前の整備を行いましょう
12月になると日ごとに気温が下がり、突然初雪が降ったり路面が凍結したりしてタイヤが滑りやすい状況になり、ブレーキやハンドル操作に影響が出る危険性があります。また、冬は暖房を使用するのでバッテリーが上がりやすく、突然エンジンがかからなくなる可能性があります。12月になる前に車の点検整備を行いましょう。
冬用タイヤに付け替えましょう。
タイヤチェーンをケースから出して点検整備し車に乗せ、雪が降っても対応できるようにしましょう。
3年以上バッテリーの交換をしていない場合は、交換を検討しましょう(バッテリーの寿命は2~3年くらいです)。また、車を運転する前のバッテリー液の点検と補充も忘れずに!
ゆとりある走行計画を立てましょう
12月は交通量が多くなり、予定どおりに進まなくてイライラすることがあります。イライラや焦りは、安全確認不足や車間距離を詰めてしまうなど運転が雑になる可能性があります。
なるべく周囲が明るい午前中に出発し、薄暗くなるまでに戻れるように、あらかじめ時間にも心にもゆとりをもてる計画を立ててから運転しましょう。
12月は不注意での交通事故を減らし良い年を迎えられるようにしましょう!
自転車は「車両」です!
コロナ感染対策の一つとして自転車を利用する人や、免許返納後の移動手段として電動アシスト自転車を使い始める高齢者の方が増えてきているそうです。利用者が増えれば事故が増えます。今回は自転車事故の防止について紹介していきたいと思います。
自転車事故で特に多いのが対自動車の信号のない交差点での出会い頭事故です。自動車との事故は過失割合に関係なく自転車側に被害が集中します。重大な事故に繋がらないために自転車の安全な乗り方を今一度確認しましょう。
自転車事故の発生状況
自転車交通事故の件数、死傷者数は年々増加傾向にあります。そのうち死傷者の4割は若者と子供が占めています。安全不確認・一時不停止、信号無視が主な原因を占めており自動車との事故が8割以上を占めています。
自転車事故のパターン
自転車は道路交通法で自動車と同じ車両に含まれています。車両としての交通ルールを守らなければ自転車側も責任を問われます。自転車はどのような状況で事故に遭ってしまうのかみていきましょう。

パターン➀ 安全不確認(急な進路変更)自転車は機動性の高い乗り物なので車道を走っている際前方に駐車している車両や障害物があった場合スピードをそのままに進路を変更して車道中央付近を走行することがあります。この時後方の安全を確認しないと乗用車に後ろから追突され事故に繋がってしまいます。パターン② 一時不停止
自転車事故はこのパターンが最も多い事故になります。
信号のない見通しの悪い交差点で自転車が交差点に進入したところ、自動車にぶつかってしまう出合い頭事故が多発しています。原因は自転車の一時停止の標識を無視して起きる場合がほとんどです。自転車側は「車両」という事を自覚して運転しなければこのような交通事故に繋がってしまいます。
パターン③ 信号無視
自転車側が信号無視をして交差点に進入し起こる事故も少なくありません。
自転車側が「信号は赤だけど自分が渡れば自動車は止まってくれるだろう」と思いこみ事故が起きてしまいます。
パターン④ 歩道上での歩行者との接触
この事故は自転車側は車道を走行していないことが原因にあります。自転車はやむを得ず歩道を走ることもあるかもしれませんがスピードを緩めず走っているとこのような事故に繋がってしまいます。
自転車の安全な乗り方
1・自転車は原則車道を通行!
自転車は車両に区分されるので原則車道を通行しま
しょう。
2・車道は左側を通行!
自転車は車道の左側を通行しなければ対面する自動
車や自転車にとって危険になります。
3・歩道は歩行者優先で車道よりを徐行
自転車も例外的に歩道を通行できることがありま
す。しかし歩道は歩行者優先の為、車道側を徐行し
て通行しなければなりません。
4・安全ルールを守る
当たり前のことですが、二人乗りをしない、並列走
行をしない、飲酒運転をしない、夜間はライトを点
灯する、信号を守る、一時停止をする等の基本的な
ルールを守らなければ事故に繋がってしまいます。
5・子供はヘルメット着用
自転車乗車中の事故による被害を軽減させるために
ヘルメットを装着しましょう。
自転車は「車両」に分類されている為、交通ルールを守らないと事故へつながるリスクが高くなる乗り物です。手軽に乗れる乗り物ですが時に相手に被害を与えてしまったり自分への被害も大きいものになる可能性を忘れず正しく乗ることを心がけましょう。
自賠責保険と任意保険の違いをご存知ですか?
交通事故に遭ってしまった際に使うことになるのが自賠責保険と任意保険です。みなさんは自賠責保険と任意保険の内容の違いは理解していますか?今回は自賠責保険と任意保険の違いについて紹介していきます。
自賠責保険について
自賠責保険は、交通事故被害者の救済を目的として、自動車などの運転者に加入が義務付けられている保険です。
自賠責保険の補償は、人の死亡やけがが対象です。ただし、眼鏡や服といった、当事者の身につけているものの破損は、人身事故の一部として扱うので、自賠責の補償対象に含まれます。
自賠責保険と任意保険の違い
自賠責保険は、車などを運転する全ての人が加入しなければならない保険です。重要なことは、人身事故が起きた時、初めに適用されるのが自賠責保険であることです。
損害額が確定したら、まずは自賠責保険で補償することになります。しかし、自賠責だけでは足りない部分があった場合、その差額を補償するのが任意保険の役割となります。

自賠責保険は加害者も被害者も請求可能である
自賠責保険のもう一つの特徴として、被害者だけでなく加害者にも、保険金を請求する権利があるという点があげられます。
被害者請求は、交通事故でけがを負った被害者は加害者が加入している自賠責保険の会社に対して、保険金の支払いを直接請求できます。
反対に、加害者側が自賠責保険を請求する加害者請求も可能です。この場合は、はじめに被害者への損害賠償を完了させてから、自分が加入している自賠責保険会社に保険金の支払いを求めることになります。
自賠責保険と任意保険における過失割合の違い
自賠責保険や任意保険には、状況ごとの過失割合が設定されています。自賠責保険と任意保険の、過失割合の考え方の違いや、保険金にどのように影響を与えるのかをみていきましょう。
交通事故による過失割合の定義
交通事故における過失割合とは、被害者と加害者それぞれが交通事故で被った損害に対して、相手方の責任がどれだけあるかを示すものです。
ほとんどの交通事故では、加害者だけでなく、被害者にも安全確認の不足などの原因があります。過失割合は、これを比率として数値化し、保険金の支払い額の修正要素とするために使われています。
具体的には、被害者側の過失に対する責任として、加害者に請求できる賠償金の金額が過失割合に応じて減額されます。過失割合が支払総額に影響するという点では、自賠責も任意保険も基本的には共通している内容です。
自賠責保険の過失割合
自賠責保険では、被害者の過失割合が7割を超えた時のみ減額(重過失減額)されます。過失割合が7割に満たない場合は、満額での支給です。
過失割合による自賠責の減額率は、死亡または重篤な後遺障害が残った場合で最大5割です。一般的な傷害事故では、2割程度の過失割合が計上されます。
任意保険の過失割合
一方、任意保険では、被害者の過失割合に応じて支払額を減額(過失相殺)します。例えば、被害者の過失割合が2割なら20%、7割なら70%が支払額から減額されるということです。
過失相殺では、交通事故の種類が死亡事故や後遺障害事故、通常の傷害事故のどれであっても過失割合への影響はありません。仮に、総額120万円の保険金請求権に対して、被害者の過失割合が5割であれば、実際の請求額は60万円となります。
こうしてみていくと、重過失減額のしくみがある自賠責保険は、任意保険に比べて、過失割合の影響を受けにくい保険だということができます。
ただし、また、被害者の過失割合自賠責保険で補償されるのは人身事故に限られ、物損の補償は過失割合に関わらず対象外です。が100%の時は、自賠責保険を請求することはできなくなります。
自賠責保険に慰謝料を請求する方法と支払限度額
次に、自賠責保険会社に慰謝料を請求する方法を見ていきましょう。自賠責から支払われる保険金の限度額は、被害者に障害や後遺障害がある場合と、死亡した場合で変わってきます。
被害者請求で自賠責保険に請求する
被害者が自賠責保険を請求したくても、交通事故による入院などで収入が途絶えてしまった場合は、生活が行き詰ってしまいます。しかし自賠責保険は、損害額が確定する前に請求することはできない決まりです。
こうした事態を防ぐため、自賠責の被害者請求には、保険会社に損害賠償額の一部を先に渡す「仮渡金制度」が認められています。仮渡金は、死亡事故で290万円、傷害は5万円~40万円です。
自賠責保険による支払限度額【傷害・後遺障害】
交通事故により傷害を負った場合の、自賠責保険での支払限度額は、被害者1名あたり最大120万円となります。この金額は、治療費や入院中の諸経費、診断書などの費用だけでなく、慰謝料や休業損害、交通事故証明書発行手数料も含めた総額です。
また、後遺障害による損害では、その後遺障害の等級や介護の必要性によって、慰謝料や逸失利益を含めた支払限度額が変わってきます。
自賠責保険による支払限度額【死亡による損害】
一方、死亡による損害では、被害者一人あたりの支払限度額は3,000万円となっています。この金額は、逸失利益や慰謝料、葬儀費用を含めたものです。
また、交通事故から死亡までに、被害者が負った傷害による損害はこの費用には含めず、最大120万円まで別途支払われます。被害者の受けた損害額が120万円を超える場合は、差額を加害者が加入する任意保険会社に請求します。
自賠責保険は被害者の過失割合が高いときに有利である
自賠責保険は、被害者側の過失割合が高い場合でも有利な制度として作られていることが分かりました。被害者・加害者のどちらにせよ、交通事故の当事者にならないのがベストです。
しかし、自分が被害者となった交通事故で過失割合が高いようであれば、自賠責保険の請求を考慮するのも一つの方法ではないでしょうか
車間距離に気をつけましょう!
道路を走行するときは、同じ車線を走る前の車が急停止したときに追突を回避できるよう車間距離を保たなければいけません。みなさんは十分な車間距離を保っていますか?
今回は、車間距離が短いことにより起きる交通事故やトラブルを通し、十分な車間距離を保つためにはどうすればよいのかをみてみましょう。
短い車間距離は追突事故を起こす危険性と、あおり運転に間違えられる可能性があります
車間距離が短いと、前の車が急停止したときに追突事故を回避できない危険性があります。慣れや経験不足から周りに流されたり、今だけは大丈夫と思い込んだりして車間距離が短くなっている方もいるのではないでしょうか。運転経験が豊富なほど適切な車間距離を忘れ、自分の感覚による車間距離へと置き換わっている可能性があります。若い世代はもとより中高年層も、運転に慣れ過ぎず安全意識をもって適切な車間距離を把握することが大切です。
また、短い車間距離は、前の車に「あおられてる?」と思わせる可能性があります。警察庁のあおり運転に関するアンケートで回答したドライバーのうち、約35%があおり運転の被害経験があると答えています。その被害内容は「後方からの著しい接近」が約82%と最も多くなりました。自身にあおる意思が無くても、短い車間距離は前の車に無用な不安やいらだちを与え、場合によってはトラブルに発展する危険性をはらんでいます。
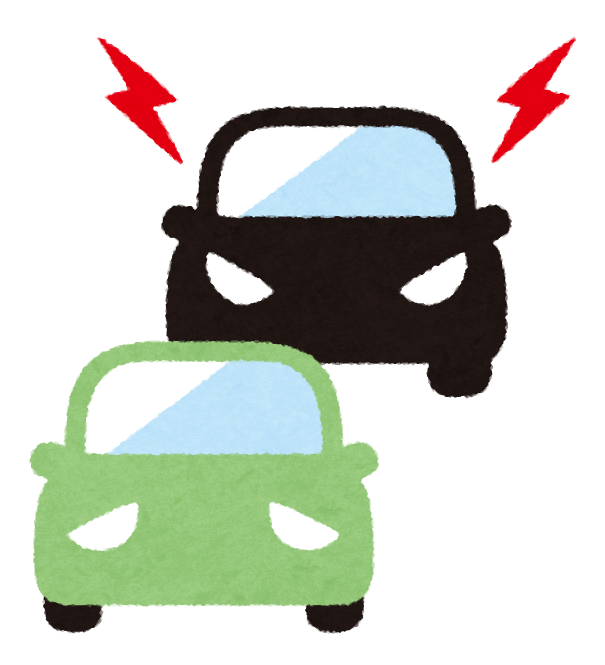
適切な車間距離とは、前の車が急停止したときに追突しないよう安全に停止できるだけの距離を保つことをいいます。一般道路では40km/hの速度での停止距離は約22m、高速道路では80km/hの速度での停止距離は約80mが必要とされますが、車を運転しながら距離を測ることは容易ではありません。では、十分な車間距離を把握するためにはどうしたらよいのかをみてみましょう。
「ゼロイチ・ゼロニ」と2秒数える車間時間を利用して車間距離を確認しましょう
車間距離測定実験によると、プロドライバーが走行した車間距離を時間に換算して「車間時間」を算出したところ、安全を感じ始める距離が約1.5秒、近すぎるとも遠すぎるとも感じない走りやすい距離が約1.8秒という結果でした。一方、統計的には車間時間が2秒以内での事故は死亡事故等の重大事故が多く、2秒以上離れていると大きな事故となっていないことが示されています。実験結果と統計的事実から、安全で走りやすいと感じる車間時間の1.8秒では実際には安全とは言えず、前の車がある地点を通過してから2秒経った後で、自分の車がその地点を通過する距離が適切な車間距離になると考えられます。
疲れや天候の悪化など運転時の状況によっては、車間距離を長くとるようにしましょう。
車が停止するまでには、運転者が危険を感じてからブレーキを踏み、ブレーキが実際に効き始めるまでの間に車が走る距離(空走距離)と、ブレーキが効き始めてから車が停止するまでの距離(制動距離)とを合わせた距離(停止距離)を必要とします。
身体が疲れているときは、危険を感じてブレーキを踏むまでの時間がかかるため空走距離が長くなるおそれがあります。いつもより車間距離を長めにとるようにしましょう。
雨天で路面が濡れているときやタイヤがすり減っているとき、重い荷物を載せているときや坂道で走行するときは、ブレーキの効きが弱くなり制動距離が長くなることがあるので、道路条件の良いときに比べて2倍の車間距離をとるようにしましょう。
秋の交通安全運動実施中です!!
9月21日から秋の交通安全運動が始まりました。
山梨県では6つの重点を掲げ交通事故ゼロを目指しています。
~秋の交通安全運動の重点~
➀子供と高齢者の安全な通行の確保
②高齢運転者の交通事故防止
③夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
④全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
⑤飲酒運転の根絶
⑥二輪車の交通事故防止
重点を6つとする趣旨は
➀次代を担う子供のかけがえのない命を社会全体で交通事故から守ることが 重要であるにもかかわらず,依然として道路において子供が危険にさらされ ていること,また,高齢者の交通事故死者数が,交通事故死者数全体の約半 数を占め,その減少が強く求められていること
②高齢運転者による重大交通事故が発生していること
③秋口における日没時間の急激な早まりとともに,例年,夕暮れ時や夜間に は,重大事故につながるおそれのある交通事故が多発し,歩行中・自転車乗 用中の死亡事故が増加すること
④自動車乗車中における後部座席シートベルトの着用率やチャイルドシート の使用率がいまだ低調であること
⑤重大事故の原因となる飲酒運転による悲惨な交通事故が依然として後を 絶たないこと
⑥秋の行楽シーズンを迎え,二輪車の通行量が増えることから二輪車の交 通事故が予想されること
となっています。

当院周辺は自転車を使う学生が多く細い道が多いため交通事故が起こりやすい地域です。今回の交通安全運動で改めて交通ルールを見直して思いやりのある運転を心がけましょう!
ドライブレコーダーの点検は行っていますか?
皆さんの車にはドライブレコーダーは付いていますか?今では普及率が50%を超えて2人に1人以上がつけているそうです。
皆さんは、ドライブレコーダーの映像をチェックしたりしていますか?実はドライブレコーダーを付けた後も色々気を付けないといけないことがあります。
①録画動作確認
最初にレコーダーを付けた頃は、たまにSDカードを取り出して中を見たりしたでしょうが、最近は確認していないという方が多いと思います。
レコーダーは動いていても、うまく録画できていない!事故に遭ったときにそんな状態では付けている意味がありません。
数カ月に1度はカードを取り出して、録画ファイルの確認を行いましょう!
②SDカードの交換
一度カードをセットしておけば、そのままずっと使えると思っている方も多いでしょう。
しかし、実はカードは消耗品で、定期的に交換してあげる必要があります。
レコーダーでは頻繁に動画を撮影し、それを何度も何度も上書きして使っているため使用頻度がとても多いんです。
そうなるとカードは非常に酷使されるため、他の電子機器での使用よりカード寿命は短いと考えた方がよいでしょう。
カードの性能にもよりますが、1~2年位をめどに交換するよう心がけましょう。
③今の時期には熱対策
夏場の暑い時期は車中温度が70度を超えることがあります。ドライブレコーダーは精密機器なので高温には弱く、いつの間にか壊れていた!なんて事態もありえるでしょう。
それを防ぐためにはドライブレコーダーやSDカードを耐熱性の高いものにする、サンシェードやカバーで直射日光を防ぐ、ヒートシンクを付けて熱を放出しやすくする、など様々な対処法があります。
今の時期はすぐに車内がサウナ状態になってしまいます。SDカードも本体も、シッカリと管理して万が一の事態に備えましょう!
帰省シーズン!交通量増加による事故に注意!
今年も早くも8月を迎えました。最近ではコロナウイルスの感染急拡大により全国の最多感染者数が日に日に更新されています。しかし今までとは違い、行動制限が発表されることはなく経済活動を維持するという声明がありました。これからお盆が近づくにつれ帰省をする方は多いと思います。今年はコロナウイルスの影響で公共交通機関を避けて車での移動を考えている方は多いのではないでしょうか?今回は交通量が増えるときの高速道路、一般同の注意点を紹介していきます。
高速道路編
・渋滞時の追突事故に注意!
帰省のシーズン中、各地の高速道路で大規模な渋滞が発生しやすくなります。渋滞の原因は坂道であったり、トンネルの出入り口付近、カーブなど車の速度が落ちやすい場所で発生しやすいです。渋滞に差し掛かったらハザードランプを点滅させ後続車両に渋滞があることを伝えましょう。
・逆走車に注意!
近年、全国的に交通量が増える季節に高速道路の逆走が後を絶ちません。逆走と聞くと高齢ドライバーを思い浮かべるかもしれませんが65歳以上の逆走件数は全体の約6割で残りの4割は65歳未満の高齢ではないドライバーに発生している状況です。
高速道路の逆走事故は通常の事故と比べて死傷事故が約5倍、死亡事故が約40倍と重大な事故に繋がります。逆走が起きやすい場所はインターチェンジ、SA・PAと本線の合流部分で発生しやすくなります。
若いドライバーで多い逆走は目的のICを通り過ぎ、パニックになった際に逆走してしまう事例が多いです。どのような理由でも高速道路上の逆走は危険ですので絶対にしてはなりません。もし、ICを通り過ぎてしまった場合は次の料金所の一般レーンで申請すれば超過料金がかからず目的のICまでの道のりを説明してくれるので焦らず次の料金所まで運転しましょう。

一般道編
・渋滞の疲労による交通事故に注意しましょう!
高速道路と同じくこれからの季節一般道も渋滞が発生すると思います。一般道の場合は歩行者、自転車などにも注意を向けなければなりません。渋滞で集中力が落ちている時に歩行者、自転車などの急な飛び出しがあるかもしれません。目的地まであと少しでも疲れを感じたら休憩を取るようにしましょう。
・住宅街での飛び出しに気をつけましょう!
夏休み中の住宅街では子供が遊びに夢中で道路に飛び出してしまうことがあるかもしれません。特に信号のない交差点付近での出会いがいら事故は多発しており注意が必要です。
7月、8月は一年の中でも交通事故の多い月です。以上の注意点を踏まえ交通事故を防止し、楽しい夏休みを送りましょう!



夏休みの交通事故に気をつけましょう
暑さもだんだん厳しくなり夏休みの季節が近づいてきました。今年は去年と違い行動制限も緩和され久しぶりの旅行や帰省をしやすくなり、各地で交通渋滞、事故が去年より多く発生しやすくなると思います。今回は夏休みに起こりやすい交通事故を防止するために気をつけるべきことを紹介したいと思います。
1.渋滞による事故に気をつけましょう
夏休みは交通量が増え自然渋滞が発生します。低速で運転を続けているとドライバーの集中力が落ち、事故が発生しやすくなります。また、ガラスから差し込む日光で体力が奪われていきます。渋滞にはまる前にこまめな休憩を取ることが大切です。可能であればドライバーを交代しながら運転しましょう。渋滞に差し掛かった場合は早めにハザードランプを点け後続車に渋滞が起きていることを伝えると交通事故の防止に繋がります。

2.夕暮れ時は早めにヘッドライトを点けましょう
日没の一時間前後は暗くなりはじめ、視界が悪くなってきます。夏休みは祭りや花火大会など夜に外出する人が増える時期です。その為早めのヘッドライトの点灯は自分の存在を相手に伝えるためにとても重要な役割をしてくれます。
3.子供との接触事故に注意しましょう
夏休みの期間中は平日の昼間など、普段子供を見かけない時間帯でも子供を見かけることが増えると思います。普段人通りの少ない道や、公園の近く、信号のない交差点などでは子供の急な飛び出しに注意しましょう。
4.飲酒運転は絶対にやめましょう
海やレジャーに出かける機会が増えると思います。開放的な気分になりつい、お酒を飲んでしまうことがあります。「運転するまで時間があるから大丈夫だろう」「汗をかいてアルコールが抜けるだろう」と安易な考えで運転すると重大な事故を起こしかねません。アルコールは短時間で抜けるものではないので運転をする予定のある方は絶対に飲酒をしないようにしましょう。



交通事故の多くが一瞬の注意不足、操作ミスで発生します。せっかくの夏休みの思い出が悲しいものにならないよう、1人1人意識しながら交通事故防止に努めましょう。


子供を交通事故から守りましょう!
新年度が始まり早くも2カ月が経過しました。子供たちも新しい環境に慣れ、登校・下校時に余裕が出たり、友達と外で遊んだりと活発に活動することが増えてきているのではないでしょうか。今回は子供の交通事故についてドライバーが気をつける点、子供たちが気をつけなければならない点を紹介していきたいと思います。
登校・下校時の注意点
・止まっている車の陰から渡らない。
止まっている車の後ろから道路を渡ると反対車線から来る車が視認できないので事故の原因となってしまいます。
・車が通りすぎても急いで渡らない
車が通り過ぎた後急いで道路を渡ろうとすると反対車線からの車が急にやってくるかもしれません。近道になるかもしれませんが、車の行きかう道路は渡らず、横断歩道を渡るようにしましょう。
・横断歩道で止まらない車に注意
信号のない横断歩道を渡ろうとしている際に手前の車が止まり渡ろうとしても反対車線の車が止まってくれるとは限りません。信号のない横断歩道を渡る時は左右の車が止まったことを確認してから渡るようにしましょう。
・歩道を走る自転車に注意しましょう。
歩道は歩行者優先、自転車は車道を走るというルールがありますがスピードを落とさず歩道を走る自転車もいるので追突を防止するためにも縦一列で歩くようにしましょう。

友達と遊んでいる際に気をつける点
・道路には絶対に飛び出さない
公園でボール遊びなどをしている際にボールが道路に転がってしまうことがあるかもしれません。子供が遊びに行く前に道路で遊ぶこと、飛び出すことの危険性をしっかり伝えてあげましょう。
・駐車場では決して遊ばない
子供たちからみたら駐車場は広く障害物が多いので鬼ごっこやかくれんぼをしたくなってしまう場所になります。遊びに夢中になって急に発進する車に気づかず事故を起こしてしまう可能性があります。
子供の交通事故の多くが急な飛び出しによって発生しています。改めて登校・下校時、遊びに行く際の危険な場所、ルールを確認し交通事故を防ぐことが重要です。
また、ドライバーの方は常に「かもしれない運転」を心がけ子供の安全を守りましょう。

高速道路上の事故を防ぎましょう!
暖かい日が多くなりお出かけ日和の日が続いています。先月から県民割を拡大し、隣県割、地域ブロック割などの制度がスタートしています。これにより高速道路を利用して旅行に出かける方もいると思います。今回は高速道路を安全に走行するために気をつけることを3つ
紹介したいと思います。
1.高速道路上での故障に注意!
高速道路は一般道と違い時速100km近い車が行き交っています。そんな中で交通事故を起こすと重大事故になりかねません。平成29年度中の高速道路事故の原因第一位はタイヤの故障で全体の約55%を占めています。次いで潤滑油のトラブルが約5%になります。
高速道路ではタイヤの車両トラブルが圧倒的に多い傾向があるとわかると思います。
高速道路を使う予定のある方は事前にタイヤの摩耗や、空気圧といった点検を行うことで故障や、事故を防止することができます。
2.歩行者に注意!
高速道路上には歩行者がいないと思いがちですが、人が車に引かれてしまう事故は少なくないのです。
事故や故障の際に高速道路上に出てしまい、後続車にひかれてしまうというケースがあり、運転者側も路肩等に停止している車を見かけたら速度を落とすなど、注意して運転する必要があります。
また、もしやむを得ず停車した場合は路肩に移動し、一般の道路の感覚で路上で行動しないように注意しなければなりません。発煙筒や三角表示板などの停止表示器材を設置し後続車両へ注意を促しましょう。また、むやみに路肩を歩かず、ガードレールの外側など安全な場所に避難するようにしましょう。
3.全席シートベルトは必ず着用しましょう!
シートベルトを着用していないと車外放出事故に繋がる可能性が上がり、死亡事故になる可能性が高くなってしまいます。
高速道路でのシートベルト着用は全席で義務化されていますが、2021年の統計で運転席、助手席のシートベルト着用率は90%以上でしたが、後部座席は約75%となっており、低い値となっています。後部座席でシートベルトを着用せずに交通事故に遭った場合、車外放出の他に前席同乗者への加害などの危険性があります。シートベルトを着用することで、車外放出による死亡事故を減らすことができます。
高速道路での交通事故を無くすために運転前には車の点検、整備を定期的に行い、同乗者にはシートベルト着用を促すなど安全対策が大切になってきます。






